こんにちは、milokitimaruです。
このブログでは「遠回りキャリア × 資産形成」というテーマで、30代後半会社員のリアルな試行錯誤を綴っています。
今回は第4回ということで、**「うまくいかなかった資産形成の過去」**を、少しだけ棚卸ししてみたいと思います。
誰でも最初はうまくいかない。でも、だからこそこれからがある。
そんな気持ちで書いてみました。
🔹 なぜ続かなかった?過去の失敗あれこれ
正直、資産形成は何度もチャレンジしてきました。
でも、そのたびに「続かない壁」にぶつかってきました。
◆ NISA口座を開設
最初は楽天証券で積立NISAをスタート。
youtubeとかの動画やインターネットで調べたことをもうそのままやってみた感じですね。
3万円/月のペースで積み立て、100万円を超えるところまで積み立てた時期もありました。
ここ数年は特に株式が伸びているということもあり、S&P500も増えていたなと思います。
…が、世間での派手な株式のニュースと比べると・・・と感じることもあり、途中で挫折。。。
「え、これだけ?」と当時は感じてしまったんです(当時は年40万円の上限だったこともありましたので)。
どれだけの時間がかかるんだろうなあ・・・と漠然と思ってしまったというのもありますね
続けることが大事だったのに、複利の効果を実感できる前に取り崩してしまいました。
※楽天証券口座の推移
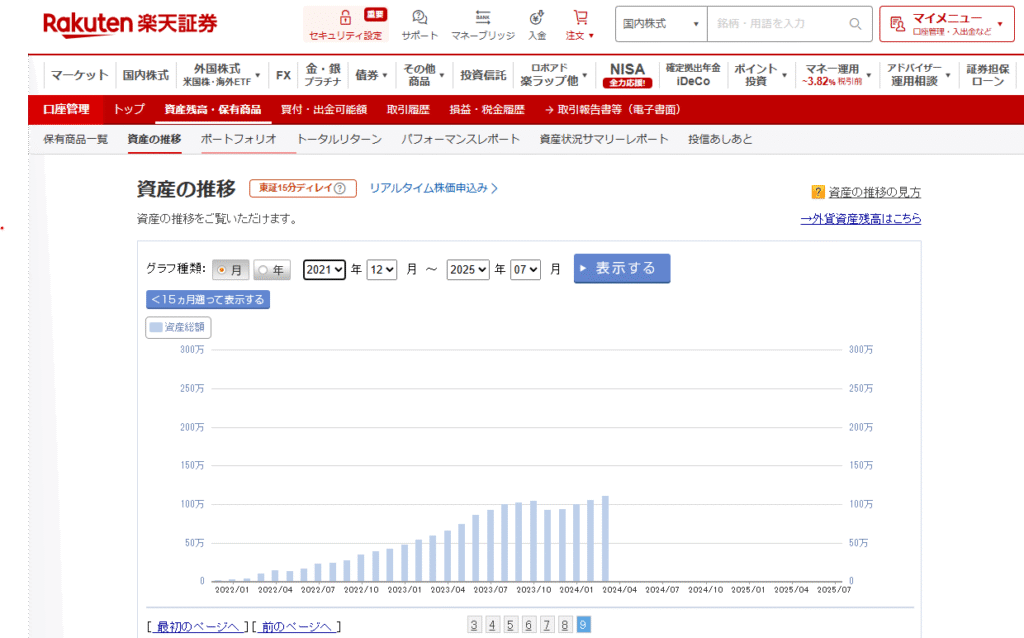
出典:楽天証券(筆者撮影)
◆ 突発的な出費で、元本を取り崩す
引っ越しなどのタイミングで、「今必要だし」と使ってしまったこともあります。
当然ながら、それまでの積立や複利効果はリセット。
「旧NISA分は新NISAにスライドできない」と知って、スライドできないなら利確しちゃおう!という考えもありました。
勝手に株価も高値感あるし、という素人考えもありましたね(笑)
◆ 忙しさから、資産状況を見なくなる
平日9時〜21時勤務の中、日々をこなすだけで精一杯。
「もう使い切るくらいが人生楽しいのでは?」という“悟りモード”になっていた時期もありました。
今でも油断すればそちらに振り切ってしまう可能性もあります。
🔸 続かなかった理由は?
今振り返ると、資産形成が「生活の外」にあったからだと思います。
- 投資を“別モノ”と考えていた
- 「余ったら投資」→でも、余らないのが現実
- 預貯金があると、気が大きくなって使ってしまう
つまり、“続ける仕組み”がないまま、気合いだけで始めていたんです。
お金を“貯める”よりも、**「すぐに使えなくなる仕組み」**の方が大事だったんですね。
なにより自分の今の年齢から、たとえば60歳ぐらいのときにこれぐらいの財産をというイメージが希薄だったというのがありますね。
🔸 今との違いはなにか?
そんな反省を踏まえて、今は以下のような方針でやっています。
◆ 自動で積み立てる(毎月・毎日)
- 投資信託:月10万円をクレカ積立(SBI証券)
- 仮想通貨:毎日2,000円(BTC 1,500円/ETH 500円)をGMOコインで
- 企業型DC:毎月1.5万円(会社+自己拠出)
“なるべく自動”であることが最重要。
考える必要がない、無駄遣いしづらくなる(そもそもの使える枠を減らす)仕組みは、自分にはすごく合っていると感じています。
◆ 「頑張らない投資」が自分には合っていた
投資に時間をかけられる人は積極運用も良いと思います。
でも、自分のような“普通の会社員”にとっては、**「いかに頑張らずに続けられるか」**がカギ。
投資は目的ではなく、手段。
だからこそ、生活に馴染む形で「無理なく続けられる設計」を大事にしています。
あ、もちろんリスク資産なので、元本割れの可能性はあります。
「確実に資産が増える」というものではないけれど、
まずはその**“第1歩目を踏み出す”こと**が、今の自分にとって大事だと感じています。
✍️ 次回予告:「投資がこわいとき、どうしてる?」
「資産が減ったらどうしよう…」「今って買いどきなのかな…」
投資に不安を感じる瞬間、誰にでもありますよね。
次回は、そんな**「不安との付き合い方」**について、自分なりの視点で書いてみたいと思います。
まだまだ手探りですが、共感してもらえたら嬉しいです。

コメント